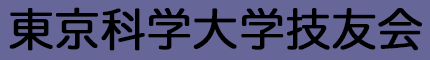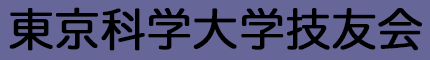|
|
| 実習科11期 1969(昭和44)年修了 |
| アタッチメント 押見 洋夫 |
| とりはずし埋没法について 勝野 正樹 |
| シェイドガイドの作り方 熊谷 章 |
| スプリットキャスト法について 栗原 ひろみ |
| 緩圧性アタッチメント 坂田 育男 |
| アタッチメント 高木 昭一 |
| 基本的歯冠の彫刻 鈴木 克彦、西脇 雅彦 |
| 実習科12期 1970(昭和45)年修了 |
| 技工料金について 杉山 進 |
| 変形の少ないレジン重合法について 勝田 彰 |
| 前歯部の個性的な排列について 栗原 幸雄、篠田 敏行 |
| とりはずし埋没法についての検討 石綿 勝 |
| ノンマトリックス法について 大石 一、宇都 憲次、後藤 賢 |
| アタッチメント(ロサーマン)について 矢作 光昭 |
| 実習科13期 1971(昭和46)年修了 |
| 陶材の研磨について 安藤 いく子 |
| ベースプレートの変形について 牛田 雅子 |
| 焼付金属の研究 小林 通宏、下沢 憲昭、永井 龍夫、荻原 光男、山中 治、牛腸 政義 |
| リベースの変形 佐藤 福芳 |
| 機能的歯冠彫刻 鈴木 時三郎、水野 行博 |
| 実習科14期 1972(昭和47)年修了 |
| 印象材と石膏との経時的変化 秋山 元治 |
| 自家製アタッチメントの強度及び適応性について 池田 鉄雄 |
| 自家製アタッチメントの分割法の研究 木股 金市 |
| 焼付金属と陶材の研究 草川 貴久 |
| 焼付金属の前ロー接の研究 越 勤 |
| 酸素ロー接の変形度 志茂野 博芳 |
| P.K.T の大型歯の製作 正田 恭三 |
| アルミナスポーセレンの強度について 滝ヶ平 誠、南谷 英夫 |
| アタッチメントの鋳接について 土平 和秀 |
| 実習科15期 1973(昭和48)年修了 |
| 後ロー着と埋没材について 山蔦 三雄 |
| 人口歯の試作(咬合小面と咬頭傾斜の明確な人口歯) 市川 正幸 |
| ダウエルピン植立器の試作 桐生 孝幸 |
| 硬質レジンの技工操作について 佐々木 進 |
| 塩酸のガス除去器の試作 関口 篤 |
| カラーガイドの試作 高崎 敏広 |
| 後ロー着について 浪原 勉 |
| レジントレーについて 牧野 公一 |
| ジャケットクラウンの適合度について 山本 さなえ |
| ダストの集塵機の試作 若林 昇 |
| 実習科16期 1974(昭和49)年修了 |
| 前歯部色調の読みとりに関する研究(幻の課題名) 加藤 一誠
16期生はまとめて「臨床例技工報告」になっていたと思いますが,実は,各自色々な研究をしているようでした.私はシェードテイキングを何とか自動化をできないものか(ポーセレンの色をうまく出せなかったため?)と材研の増原先生の所へ何度かお邪魔させていただきました.今から30年も前のことです.結局,文献のレビューだけで終わってしまったのですが・・・現在は電子機器の発達によって簡単にできるようになってしまいました. |
| 実習科17期 1975(昭和50)年修了 |
| 全部鋳造冠の鋳造後の浮きあがりについて 井上 清俊、岡本 方晴、三上 真 |
| 陶材焼付金属と高温埋没材の混液比と攪拌時間による鋳肌状態について 渡邊 清志、野村 種生 |
| 実習科18期 1976(昭和51)年修了 |
| 支台軸面の粗度による鋳造冠の浮き止まりについて 池田 浩之、岡野 憲仁、青木 智彦 |
| マージンの支台形態の相違による研磨目減り量の違いについて 川崎 一夫、神津 祥一、近藤 素規 |
| 実習科19期 1977(昭和52)年修了 |
| 印象材の時間的変化による模型変形 山鹿 洋一、渋谷 修一 |
| ポーセレンの問題点(理工・臨床・技工それぞれの視点からの問題点のアンケート調査) 近藤 厚 |
| 印象処理、ラバー印象の歯肉部を加熱ワックスで処理することによる熱変化が模型におよぼす影響について 和田 日出夫 |
| 臨床報告 真砂 克也、渋谷 了暎 |
| 実習科20期 1978(昭和53)年修了 |
| 硬質レジンの色調と物性との関係 熊谷 信雄、丁 宗治、日高 洋一 |
| 流し込みレジンの技工操作(埋没方法について) 飯塚 俊夫、熊倉 進 |
| 超硬質レジンの機械的性質 白井 一弥、鈴木 悟 |
| 新しい接着剤4-META(4-メタクリロキシエチルトリメリット酸無水物) 斉藤 真且、山口 文雄 |
|