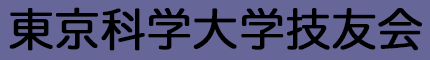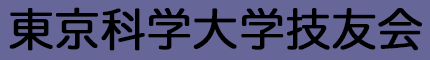|
|
| 実習科1期 1959(昭和34)年修了 |
| 歯科補綴物製作に於ける各ケース別所要時間の測定について 小川 八郎 |
| 各種調整法に依る鋳造体の比較と臨床技工上の誤差について 高木 良三 |
| ギージー氏簡易咬合器上における模型の前・後・左右の位置関係から生じた、クリステンゼン氏現象の差異について 佐川 広光 |
| 各種埋没材による床用レジンの耐磨耗性について 柴田 桂太 |
| 金属板の圧印に関する精度について、とくに咬合圧印について 坪井 恭一 |
| レジン床の変形に関する研究 森脇 正光 |
| 実習科2期 1960(昭和35)年修了 |
| アルギン酸系分離剤使用術式の比較考察 坂庭 武 |
| レジン床に埋入する所謂加強線について 佐藤 研造 |
| 鉤用線の熱処理、無処理における各鉤用線の撓みと永久変形について 塩田 幸男 |
| レジン床修理の接合強さに関する研究 鈴木 康吉 |
| レジン継続歯の変色防止に関する研究 高橋 勇 |
| ある種の20K金合金の技工操作による表面あらさの変化について 辻 康弘 |
| 実習科3期 1961(昭和36)年修了 |
| 学校の都合により卒論行われず 石田 豊巳、今野 冨夫、加藤 猛、川島 耕二、鈴木 義行 |
| 実習科4期 1962(昭和37)年修了 |
| ポーセレンジャケットクラウンについて 岩本 猛、篠田 章、加賀谷 忠樹、田中 朝見、久永 博 |
| 実習科5期 1963(昭和38)年修了 |
| 鋳造鈎の直接法と間接法の適合精度について、とくにインレーワックス、パラフィンワックスについて 安西 時良 |
| 複写鉛筆による埋没材模型への再現法について 中原 健雄 |
| 型ごと埋没鋳造法における鋳ばり発現状態と鋳肌粗土について 森 博史 |
| 実習科6期 1964(昭和39)年修了 |
| ポストクラウン陶歯の強度試験 横井 欣弘、斎木 好太郎、大井 修多、加納 清
当時流行していたポストクラウン陶歯の強度を計測するもので、切端に加重を加え破折するまでの耐加重を調べた。付随する研究として人工歯切縁の加重分布状態を高弾性試験機にて検出したことは過去に見られない実験だったと記憶しています。試験体の製作に際して内部歪を入れないように細心の注意を払って作業したことが特に印象的です。(指導:補綴学教室 吉田恵夫助教授) |
| レジン全部床義歯の重合時における変形について 柳原 和巳 |
| 歯科用レジン床内に埋入する補強材の効果 関口 清 |
| レジン重合時に於ける歯列のくるいについて 印南 栄一、落合 修一 |
| 初期乾燥を100℃から行った場合と300℃から行った場合との鋳型内面の粗土及び、鋳造体精度についての研究 松浦 俊男 |
| 実習科7期 1965(昭和40)年修了 |
| ポーセレンジャケットクラウンの破折試験 伊藤 布久美、坂本 吉雄、塔本 邦男、垣内 昭仁 |
| 印象材の種類によるロングスパーンの変形度 小竹 俊夫 |
| 新しく考案されたギルモア型アタッチメントの製作法 野村 順雄 |
| 陶歯とレジン歯の対咬組み合わせによる全部床義歯の自動削合用研磨材について 時田 正人 |
| 実習科8期 1966(昭和41)年修了 |
| リバースピンに関する研究 栗崎 秀樹、高橋 忍 |
| 新乾式重合機によるレジン床の重合条件に関する研究 杉山 範政 |
| サーモプレス機を利用して義歯用アクリル樹脂の乾熱重合を行った場合の分離材(アルギン酸系分離剤)の分離効果について 中谷 勲 |
| 技工室の設計 白川 忠広 |
| クラスププライヤーの種類と特性、その改良について 曲山 義康 |
| 技工室の設計 山本 靖広 |
| 実習科9期 1967(昭和42)年修了 |
| セラムコの強度試験 安藤 申直、益田 徳雄 |
| 審美的な前歯部歯肉色のレジン塡入法 林 賴雄 |
| 加熱重合義歯床用アクリル樹脂のフラスコ塡入から加熱までの時間によるヌープ硬度及び引張り強度への影響 早川 真佐緒 |
| ネイデンタルサベヤーの改良 滝 千雄 |
| 歯科用材料自動攪拌機製作のための粉量計・水量計の試作 木村 忠史 |
| 実習科10期 1968(昭和43)年修了 |
| 技工机について 稲葉 実 |
| 交叉咬合排列とその削合 木下 文雄 |
| 技工用具の改良(バースタンド) 佐粧 悟 |
| 陶材ジャケットクラウンの自然感の再現法 妹尾 輝明、藤井 孝二 |
| 緩圧性アタッチメントの使用術式 迎 繁樹 |
| 焼付陶材冠のステップ模型 吉田 比呂志 |
|